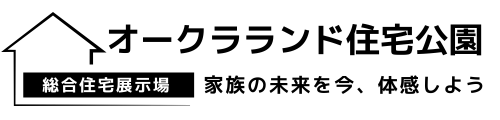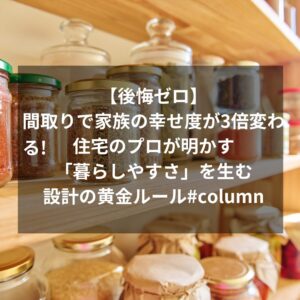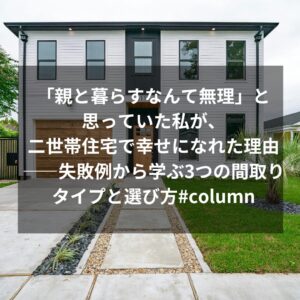階段のない暮らしが人生を変える―平屋に住んで初めて分かった「本当の豊かさ」とは#column
この記事を読めば分かること
「平屋って実際どうなの?」という疑問を持つあなたに、平屋暮らしの本質をお伝えします。単なる間取りの違いではなく、暮らし方そのものが変わる平屋の魅力を、住まい手の実体験と建築のプロが重視する設計哲学から紐解きます。家づくりで後悔しないための具体的なチェックポイントと、あなたの家族に平屋が合っているかを判断する基準まで、この記事一つで平屋の全体像が掴めます。
はじめに
朝起きて、寝室からリビングまで歩く距離はわずか数歩。子どもの笑い声も、料理の匂いも、家族の気配が自然と感じられる。そんな暮らしを想像したことはありますか?
住宅展示場を訪れると、多くの人が「なんとなく平屋っていいな」と感じます。でも同時に「土地が広くないとダメなんじゃないか」「コストが高そう」「本当に自分たちに合っているのか」という不安も浮かんでくるものです。
実は今、平屋を選ぶ人たちの考え方が大きく変わってきています。「老後のため」という消極的な理由ではなく、「今を豊かに暮らすため」という積極的な選択として平屋を選ぶ家族が増えているのです。
30代の若い夫婦が、70代のシニア世代が、それぞれ異なる理由で「平屋こそが理想の住まい」と確信する背景には何があるのでしょうか?この記事では、実際の住まい手の声と、数多くの平屋を設計してきたプロの視点から、平屋という選択の本質に迫ります。
あなたが「なんとなくいいな」と感じていた平屋の魅力が、この記事を読み終わる頃には「これこそが自分たちの求めていた暮らしだ」という確信に変わるはずです。
なぜ今、平屋なのか?―時代が求める「ちょうどいい」暮らし
住宅雑誌のページをめくると、必ずと言っていいほど平屋特集が組まれています。ある出版社の編集者はこう明かします。「平屋特集号は、他の号と比べて明らかに売れ行きが違うんです。年齢層も幅広く、20代から70代まで満遍なく購入されています」
この現象は何を意味しているのでしょうか?
平屋とは、すべての生活空間が一つのフロアに収まる一階建ての住宅です。聞けばシンプルな話ですが、この「すべてが同じ高さにある」という特徴が、現代人が抱える様々な課題を解決する鍵となっているのです。
「垂直移動」が生む見えないストレス
二階建て住宅で暮らしていると、私たちは無意識のうちに一日何度も階段を上り下りしています。洗濯物を二階のベランダに干すため、忘れ物を取りに子ども部屋へ、寝る前に二階へ上がる―。
若く健康な時はこの動きを当たり前と感じますが、妊娠中や小さな子どもを抱いている時、仕事で疲れ切っている時、風邪をひいている時はどうでしょう?階段という「垂直移動」が、じわじわとストレスとして蓄積していきます。
30代の子育て世代が平屋を選ぶ理由の一つが、この「見えないストレス」からの解放です。「子どもがハイハイしている時期、階段に柵をしても常に心配でした。平屋なら、そもそもその心配がゼロになる」という声は、多くの親が共感するポイントでしょう。
家族の距離が自然と縮まる空間
「息子が中学生になってから、二階の部屋にこもりがちで。階段を上がってわざわざ部屋に行くのも気が引けて、気づけば会話が減っていました」
こんな悩みを持つ親は少なくありません。二階建ての場合、個室が二階にあることで、物理的な距離だけでなく心理的な距離も生まれてしまうのです。
一方、平屋では個室がリビングの延長線上にあります。完全に孤立するわけではなく、リビングで過ごす家族の気配が自然と伝わる。思春期の子どもにとっても、「適度な距離感」が保たれるのです。
「部屋の前を通りかかった時に『今日の夕飯、好きなもの作るけど何がいい?』なんて自然に声をかけられる。それだけで会話が生まれるんです」という親の言葉には、平屋ならではのコミュニケーションの形が表れています。

「終の棲家」から「始まりの家」へ―平屋に対する価値観の変化
かつて平屋は「老後を見据えた家」というイメージが強くありました。しかし今、その価値観は大きく変わっています。
「私たちはまだ32歳と30歳。子どもも3歳と1歳です。でも最初から平屋一択でした」と語るのは、長野市に平屋を建てた若い夫婦です。
「老後のことを考えたわけじゃありません。今、子どもたちが安全に走り回れる環境が欲しかった。共働きで忙しい中、家事動線を短くして効率的に暮らしたかった。そして家族みんなが同じ空間にいる温かさを大切にしたかった。それが平屋を選んだ理由です」
この言葉に象徴されるように、平屋は「人生の終わりに備える家」ではなく、「人生の始まりを豊かにする家」として選ばれているのです。
「憧れ」の正体―シンプルであることの贅沢
「正直に言うと、平屋ってかっこいいじゃないですか。それが一番の理由かもしれません」
こう率直に語る人は意外と多いものです。そしてこの「なんとなくいい」という感覚は、実は深い意味を持っています。
平屋の外観は、周囲を圧迫しません。低く横に広がる屋根のラインは、風景に溶け込み、穏やかな印象を与えます。特に自然豊かな信州の環境では、山々の稜線と呼応するような平屋の佇まいが、見る人に安らぎを与えるのです。
「シンプルであること」は、実は最も贅沢なことかもしれません。余計な装飾や複雑な構造ではなく、本質的な美しさを追求した結果としての平屋。その美学が、多くの人を惹きつけているのです。
建築のプロが明かす―後悔しない平屋をつくる6つの鉄則
「平屋は簡単そうに見えて、実は設計が非常に難しい建物なんです」
20年以上平屋を設計してきたベテランプランナーは、こう語ります。シンプルだからこそ誤魔化しが効かず、設計者の力量が如実に現れる。それが平屋なのです。
では、長く快適に暮らせる平屋をつくるために、プロは何を重視しているのでしょうか?実際の設計現場で実践されている6つの鉄則をご紹介します。
鉄則1:「引き算の美学」―外観デザインは足すより引く
平屋の外観デザインで最も陥りやすい失敗は、「あっさりしすぎて物足りない」と感じて、あれこれ装飾を足してしまうことです。
「平屋は大きな一つの屋根でシンプルにまとめるからこそ美しい。でも何もしないと確かに単調になる。だから私たちは『引き算』で考えます。何を足すかではなく、何を際立たせるか」
例えば、玄関に向かう軒の出を深く取ることで、そこに生まれる陰影が外観に表情を与えます。外壁を真っ白にしたなら、一部だけ木を張ることで、白が際立ち、木の温もりも際立つ。
異素材の組み合わせで生まれる上質感
塗り壁と板張り、黒い金属と木、コンクリートと漆喰―。異なる素材を効果的に組み合わせることで、シンプルながら奥行きのある外観が生まれます。
ある設計事例では、白い漆喰壁の一面だけを焼杉板で覆いました。白と黒のコントラストが美しく、遠くから見ても一目で「あの家だ」と分かる個性が生まれたのです。
軒と庇が生む「日本らしさ」
平屋の魅力の一つに、深い軒があります。日本の伝統的な民家のように、軒を深く出すことで、夏の強い日差しを遮り、雨の日でも窓を開けられる。この機能性と美しさを兼ね備えた「軒」こそ、平屋の真骨頂です。
「外観デザインで最も大切なのは、10年後、20年後も飽きないこと。流行を追うのではなく、普遍的な美しさを追求する。それが平屋の設計哲学です」
鉄則2:天井の「高低差」で空間に物語を生む
「平屋だからこそできる空間演出があります。それが天井の使い方です」
二階建ての一階部分は、どうしても二階の床が天井になるため、高さに制約があります。しかし平屋には上階がないため、天井の高さを自由に設計できるのです。
リビングの一部を吹き抜けのように高く
家族が集まるリビングの天井を斜めに立ち上げ、一番高いところで4メートル以上確保する。そこに太い梁を渡し、その存在感を際立たせる。
「天井が高いだけで、人は開放感を感じます。でもすべてを高くする必要はありません。寝室や書斎は逆に天井を低めにすることで、落ち着いた空間になる。この『高低差』が空間に物語を生むんです」
構造を「隠さない」デザイン
通常の住宅では、柱や梁といった構造材は天井や壁の中に隠されます。しかし平屋では、この構造材をあえて見せることで、ダイナミックで温もりのある空間が生まれます。
「柱と梁が組み合わさる姿は、日本の伝統建築から続く美の形。それを現代の暮らしに取り入れることで、新しいのに懐かしい、不思議な心地よさが生まれます」
ある施主は「天井を見上げた時、太い梁が力強く渡っている姿に、いつも安心感を覚えます。この家が自分たちを守ってくれている、そう実感できる」と語っています。
鉄則3:「風と光の設計」―見えない要素こそ命
平屋で最も難しいのが、採光と通風の確保です。
二階建てなら、二階の部屋は必然的に明るく風通しも良くなります。しかし平屋では、すべての部屋が横並びになるため、建物の中央部分が暗く風通しの悪い「デッドゾーン」になりやすいのです。
「平屋の設計では、まず敷地の『風の道』と『光の入り方』を徹底的に調べます。南からの光だけでなく、東西からの光、周辺の建物が落とす影、季節による太陽高度の変化―。すべてを計算に入れます」
室内窓と地窓の戦略的配置
廊下や洗面所など、どうしても窓を取りにくい場所には、隣の部屋との間に室内窓を設けます。これにより、光が部屋から部屋へと連鎖的に届き、家全体が明るくなります。
また、足元に設ける「地窓」も効果的です。低い位置から入る光は、壁や天井を照らし、間接照明のような柔らかな明るさを生み出します。
中庭という選択肢
敷地に余裕があれば、コの字型やロの字型の配置にして、中庭を設ける方法があります。プライバシーを確保しながら、すべての部屋が中庭に面して明るく風通しの良い環境を実現できます。
「中庭のある平屋に住むお客様は、『外出しなくても、庭で過ごす時間が本当に豊か』とおっしゃいます。外から見えない庭だからこそ、気兼ねなくくつろげる。これは平屋ならではの贅沢です」
鉄則4:「廊下ゼロ」を目指す―無駄を削ぎ落とす勇気
「平屋で最も無駄なのが廊下です。できる限り廊下をなくし、部屋から部屋へ直接アクセスできる間取りを目指します」
二階建てでは、階段ホールから各部屋へ廊下が伸びる間取りが一般的です。しかし平屋では、この発想を捨てる必要があります。
リビングを「通過点」にする設計
各部屋へ行くために、必ずリビングを通る間取り。一見不便そうですが、実はこれが家族のコミュニケーションを自然に生み出します。
「朝起きて自分の部屋から出たら、必ずリビングを通る。そこで『おはよう』という挨拶が生まれる。たったそれだけのことですが、家族の絆を強くする大きな要素になります」
個室の扉は2方向につける
子ども部屋に扉を2つ設ける方法もあります。リビング側からも、寝室側からもアクセスできることで、廊下を作る必要がなくなります。
将来的に部屋を分割したり、用途を変更する際にも柔軟に対応できる。この「可変性」も平屋設計の重要な視点です。
鉄則5:「内と外の曖昧さ」―土間とデッキが暮らしを変える
「平屋の最大の魅力は、すべての部屋が地面とつながっていること。この特性を活かさない手はありません」
平屋では、どの部屋からも直接庭に出ることができます。この特性を最大限に活かすのが、土間とウッドデッキです。
土間サロンという新しい暮らし方
玄関から続く広い土間空間を、単なる通路ではなく「サロン」として設計する。そこにテーブルと椅子を置き、食事や作業ができるスペースにする。
「土間は室内でありながら、靴のまま過ごせる。庭仕事の後、土のついた野菜をそのまま洗って調理できる。薪ストーブを置いて、暖を取りながら外の景色を眺められる。この『内でも外でもない』空間が、暮らしに豊かさをもたらします」
ウッドデッキは「もう一つのリビング」
リビングから続くウッドデッキを、軒下に収めて設計する。雨の日でも使え、強い日差しも遮られる。そこは事実上「屋外リビング」として機能します。
「週末の朝、デッキでコーヒーを飲みながら新聞を読む。子どもたちはデッキでシャボン玉遊び。夕方には夫婦でビールを飲みながら夕日を眺める。生活空間が自然と外まで広がっていくんです」
ある施主は「平屋に住んで初めて、『家に庭がある』ことの意味が分かりました。二階建ての時は庭があっても使わなかった。でも平屋になったら、庭が暮らしの一部になった」と語っています。
鉄則6:「可変性」と「プライバシー」の両立―未来を見据えた設計
家族は変化します。子どもは成長し、やがて巣立つ。夫婦二人の時間が戻ってくる。この変化に柔軟に対応できる住まいこそ、長く愛される家です。
「平屋は二階建て以上に、将来の変化を見据えた設計が必要です。なぜなら、すべてが同じフロアにあるため、最初から用途を固定してしまうと、後で変更が難しくなるからです」
「今は開けて、将来は閉じる」設計
子どもが小さいうちは、広いワンルームのように使える空間。将来個室が必要になったら、可動式の間仕切りや引き戸で簡単に2部屋に分けられる設計にしておく。
「大切なのは、配線と収納の位置。最初から『ここで部屋を分ける可能性がある』と想定して、コンセントやクローゼットを配置しておくことです」
適度な距離感を生む「ずらし」のテクニック
リビングと寝室が隣り合う場合、完全に壁で仕切るのではなく、入口の位置を「ずらす」ことで、視線が直接入らないよう工夫します。
「ドアを開けた時に中が丸見えにならないよう、あえて入口を角に配置する。たったこれだけで、プライバシーが格段に守られます」
特別な鉄則:災害リスクを正面から考える
2019年の台風被害以降、長野県では浸水リスクを気にする声が増えました。平屋を検討する際、この点は避けて通れません。
「ハザードマップで浸水リスクが高い地域の場合、正直にお伝えします。『平屋は不向きかもしれません』と。でもどうしても平屋がいいという場合、小屋裏スペースやロフトを避難場所として設計することもあります」
建物を少し高い位置に配置する、基礎を高くする、などの対策も可能です。大切なのは、リスクを正しく認識し、それに対する備えを設計に組み込むことです。
「家は家族の命を守る場所。だからこそ、美しさや快適さだけでなく、安全性も妥協しない。それがプロの責任です」
平屋で失敗しないために―見落としがちな3つの落とし穴
平屋には多くの魅力がありますが、注意すべき点もあります。後悔しないために、必ず確認しておくべきポイントを3つご紹介します。
落とし穴1:土地の広さと建築コストの関係
「平屋は広い土地が必要」というイメージがありますが、実際はどうでしょうか?
確かに平屋は、同じ延床面積の二階建てと比べて、必要な土地面積は広くなります。しかし重要なのは「何坪必要か」ではなく、「その土地で理想の暮らしができるか」です。
「30坪の平屋でも、設計次第で4人家族が十分快適に暮らせます。大切なのは坪数ではなく、空間の使い方です」
一方、建築コストについては正確な認識が必要です。階段がない分コストが下がる印象がありますが、実際は基礎と屋根の面積が大きくなるため、坪単価は二階建てより高くなることが多いのです。
「総額で比較すると、同じ広さなら平屋の方が2〜3割高くなることが一般的です。ただし、将来のメンテナンスコストを考えると、トータルでは差が縮まります」
落とし穴2:プライバシーと防犯への配慮不足
すべての部屋が地面に接している平屋は、外から見られやすく、防犯面での不安を感じる方もいます。
「平屋だからこそ、外構計画と一体で考える必要があります。塀や生垣の配置、窓の高さや位置、照明計画―。すべてを総合的に設計することで、プライバシーと防犯性を確保できます」
高窓や中庭を活用することで、外から見えないけれど明るく開放的な空間を作ることも可能です。
落とし穴3:将来の変化を想定していない間取り
「今の家族構成だけで間取りを決めてしまい、後悔する方は少なくありません」
子どもが巣立った後、広すぎる個室をどう使うか。親の介護が必要になった時、部屋をどう配置するか。こうした「未来のシナリオ」を複数想定して設計することが重要です。
「5年後、10年後、20年後―。少なくとも3つの時間軸で間取りをシミュレーションします。そうすることで、長く愛される家が生まれます」
まとめ―平屋は「暮らし方」を選ぶこと
平屋という選択は、単に建物の形を選ぶことではありません。それは「どう暮らしたいか」という、人生の価値観を選ぶことです。
階段のない暮らしは、家族の距離を縮め、日々の動線を短くし、心身の負担を軽減します。すべての部屋が地面とつながることで、自然との関係が親密になり、季節の移ろいを身近に感じられるようになります。
そして何より、「シンプルであることの豊かさ」を実感できるのが平屋です。余計なものを削ぎ落とし、本質だけを残した空間。そこには、現代人が失いかけていた「丁寧な暮らし」が息づいています。
「平屋に住んで、人生が変わりました」
多くの住まい手がこう語ります。それは決して大げさな表現ではありません。住まいが変わることで、日々の過ごし方が変わり、家族との関係が変わり、自分自身の心の在り方まで変わっていく。
あなたが「なんとなく平屋っていいな」と感じているその直感は、きっと正しいのです。その直感を、具体的な形にしていくプロセスこそが、家づくりの醍醐味。
一生に一度の家づくり。後悔のない選択をするために、まずは一度、平屋という暮らし方を真剣に検討してみてはいかがでしょうか。
窓を開ければ季節の風が吹き抜け、家族の笑顔が自然と集まる。そんな暮らしが、あなたを待っています。
1つのモデルハウスの見学時間は1時間以上をお勧めいたします。余裕を持って、当日の予定を組みましょう。
モデルハウス見学予約の
4つのメリット
✅ 1.サクサク見学
待ち時間なくスムーズに見学できるので、貴重な時間を有効活用できます。家族との大切な週末を有意義に過ごせます。
✅ 2.効率よく見学!
複数のモデルハウスをまとめて見学できるので、効率的に情報収集が可能です。自分に最適な住まいを一度に比較検討できます。
✅ 3.専門性の高いスタッフ
専門知識を持ったスタッフがあなたの要望に合わせて丁寧に対応。理想の住まいを見つけるためのアドバイスが受けられます。
✅4.当日のやりとりがスムーズ
事前に質問を伝えられるので、当日の見学がスムーズに進みます。重要なポイントをしっかり確認でき、安心して見学が楽しめます。