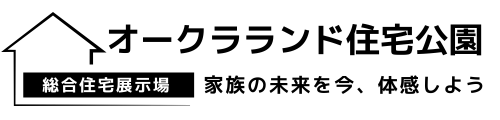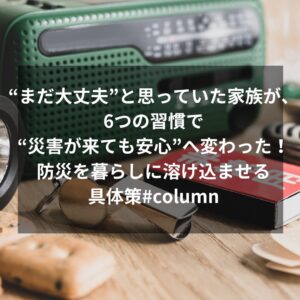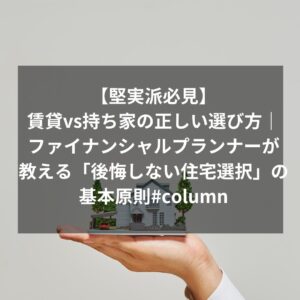「賃貸のままで1,500万円も損していた」68歳で気づいた住居費の恐ろしい真実#column
この記事を読めば分かること
この記事では、定年退職後に自分の住居選択がいかに大きな損失を生んでいたかを知った男性の実例を通して、住居費の本当のカラクリを学べます。30年間で1,500万円を無駄にした賃貸生活の落とし穴、老後資金を倍増させる「逆転の住宅戦略」、そして今からでも間に合う「人生後半の住まい革命」まで、年代を問わず知っておくべき住居費の新常識を詳しく解説します。
はじめに
「息子に言われて計算してみたら、ゾッとしました」
そう語るのは、今年68歳になった田村義彦さん(仮名)です。定年退職を機に息子から「お父さん、今まで家賃にいくら払ったか計算してみたら?」と言われて電卓を叩いた時の衝撃は、今でも忘れられないと言います。
結果は驚愕の「1,500万円」。30年間の賃貸生活で支払った家賃の総額でした。
「同じ金額で家を買っていたら、今頃は家もあって、老後資金も倍はあったでしょうね」と田村さんは苦笑いを浮かべます。しかし、話を聞いていくと、田村さんには68歳から始めた「逆転の住宅戦略」があり、それが思わぬ成果を上げていることが分かりました。
今回は、多くの人が陥りがちな「住居費の落とし穴」と、年齢に関係なく実践できる「お金を増やす住まい術」について詳しくご紹介します。
1. 30年間で消えた1,500万円の正体とは
賃貸生活の「見えないコスト」を全て計算してみた
田村さんが息子と一緒に算出した、30年間の住居関連支出の詳細をご覧ください。
30年間の賃貸住居支出(詳細)
- 家賃:月5万円×360ヶ月=1,800万円
- 更新料:2年ごと15回×5万円=75万円
- 引越し費用:6回×25万円=150万円
- 敷金・礼金:6回×15万円=90万円
- 火災保険:年1.5万円×30年=45万円 総支出:2,160万円
「家賃だけじゃなくて、こんなに付随費用があるなんて思いませんでした」と田村さん。特に引越し6回は、転勤や家族構成の変化によるものでした。
「同じお金で家を買っていたら」のシミュレーション
息子が作成したシミュレーションでは、以下のような結果が出ました。
もし2,000万円で家を購入していた場合
- 住宅ローン:月6.5万円×25年=1,625万円(金利込)
- 固定資産税:年8万円×30年=240万円
- 修繕費:30年間で200万円
- 火災保険:年1万円×30年=30万円 総支出:2,095万円 残る資産:家(築30年で評価額500万円)
賃貸との差額
- 支出差:65万円(賃貸の方が高い)
- 資産差:500万円(家が残る) 実質的な差額:565万円
さらに、住宅ローン完済後の25年間(68歳〜93歳)は家賃支出がゼロになることを考えると、差額は1,500万円を超えることになります。

2. 68歳で始めた「人生逆転の住宅投資」
退職金を元手にした「最後の大勝負」
田村さんは定年退職と同時に、退職金1,200万円を元手に中古住宅を購入する決断をしました。
購入した物件の詳細
- 価格:980万円(築25年・3LDK)
- リフォーム費用:220万円
- 購入諸費用:100万円 総投資額:1,300万円
「最初は『年寄りが家を買うなんて』と周りから反対されました。でも計算してみると、これが最後のチャンスだと思ったんです」
予想外の「家賃収入」が生まれた理由
田村さんの家には特別な仕掛けがありました。リフォーム時に2階部分を独立した1Kアパートに改造し、賃貸に出したのです。
賃貸部分の収支
- 家賃収入:月4万円×12ヶ月=48万円/年
- 管理費・税金等:年8万円 純収入:40万円/年
「まさか自分が大家さんになるとは思いませんでした。でも月4万円の収入があるおかげで、実質的な住居費がゼロになったんです」
老後の生活が激変した「安心感」
家を持つことで、田村さんの老後生活は大きく変わりました。
精神面での変化
- 家賃の心配がなくなった安心感
- 「終の住処」があるという安定感
- 孫が遊びに来やすくなった喜び
- 近所付き合いが深くなった充実感
経済面での変化
- 月5万円の家賃支出がゼロに
- 月4万円の家賃収入が発生
- 実質的な収支改善:月9万円、年108万円
「年金生活でも、以前より余裕のある暮らしができています」と田村さんは満足そうに語ります。
3. 「住居費革命」で老後資金が倍増する仕組み
78歳時点での資産予測が衝撃的
田村さんの息子が作成した10年後(78歳時点)の資産予測をご紹介します。
賃貸を続けていた場合
- 10年間の家賃支出:600万円(月5万円×120ヶ月)
- 残る貯蓄:700万円(現在1,300万円−600万円)
- 住む場所:賃貸(資産価値ゼロ)
住宅購入した場合(実際の選択)
- 10年間の家賃収入:400万円(年40万円×10年)
- 増加した貯蓄:1,700万円(現在1,300万円+400万円)
- 住む場所:持ち家(推定価値600万円) 実質資産:2,300万円
その差は何と1,000万円以上!「息子に『お父さん、ナイス判断!』と褒められました」と田村さんは嬉しそうです。
「人生100年時代」の住居戦略
田村さんの成功例から見える、超高齢社会での賢い住居戦略をまとめました。
60代での住宅購入メリット
- 退職金を有効活用できる
- 住宅ローンに頼らず現金購入が可能
- 相続対策としても有効
- 賃貸併用で収入源を確保
注意すべきポイント
- 将来のバリアフリー化を考慮した物件選び
- 医療機関や商店街へのアクセス
- 管理しやすい規模・構造
- 相続時の処分のしやすさ
4. 年代別「住居費で損しない」完全ガイド
20代・30代:「賃貸か購入か」の正解
田村さんの経験を踏まえた、年代別の住居戦略をご提案します。
20代前半:賃貸が有利
- 転職・結婚などライフイベントが多い
- 頭金を貯める期間として活用
- 年収の25%以内の家賃で生活
20代後半〜30代:購入タイミングを見極める
- 結婚・出産で住環境のニーズが固まる
- 住宅ローン控除などの制度を最大活用
- 35年ローンでも完済年齢が65歳以下
40代・50代:「住み替え」で資産を最大化
40代:教育費との両立戦略
- 子どもの教育環境を重視した立地選び
- 将来の住み替えを考慮した資産性
- 共働き世帯の利便性確保
50代:老後を見据えた最終住み替え
- 退職後の生活を想定した立地・間取り
- 住宅ローン完済時期の調整
- 相続対策も考慮した物件選択
60代以降:田村さん式「逆転戦略」
60代前半:最後の住宅投資チャンス
- 退職金を活用した現金購入
- バリアフリー・利便性重視
- 賃貸併用による収入確保
70代以降:住み慣れた家での安定生活
- 大規模修繕の実施
- 見守りサービス等の導入
- 相続準備の開始
5. 「住居費で失敗しない」ための5つのチェックポイント
チェックポイント1:ライフサイクルコストの正確な把握
田村さんが後悔したように、住居費は家賃や住宅ローンだけではありません。
賃貸の隠れたコスト
- 更新料(2年ごと)
- 引越し費用(転居のたび)
- 敷金・礼金(転居のたび)
- 家賃の上昇リスク
持ち家の隠れたコスト
- 固定資産税(毎年)
- 修繕・メンテナンス費用
- 火災・地震保険料
- 金利上昇リスク(変動金利の場合)
チェックポイント2:将来の収入変化への対応力
リスクシナリオの検討
- 転職・失業による収入減
- 病気・介護による支出増
- インフレによる実質収入減
- 年金支給額の削減
対応策の準備
- 収入減に耐えられる住居費レベルの設定
- 緊急時の住み替え計画
- 副収入源の確保(賃貸併用など)
チェックポイント3:地域の将来性評価
田村さんが住宅購入時に重視したのは、地域の将来性でした。
評価すべき要素
- 人口動態(増加傾向か減少傾向か)
- インフラ整備計画(駅・道路・商業施設)
- 医療・介護施設の充実度
- 災害リスクの程度
チェックポイント4:家族構成変化への対応力
想定すべき変化
- 子どもの独立
- 親の介護・同居
- 配偶者との死別
- 健康状態の変化
対応できる住宅の条件
- 部屋数・間取りの変更可能性
- バリアフリー化の容易さ
- 売却・賃貸の可能性
- 相続時の分割しやすさ
チェックポイント5:税制・補助制度の最大活用
活用可能な制度
- 住宅ローン控除
- 住宅取得等資金贈与の非課税枠
- 長期優良住宅等の特例
- 各自治体の補助制度
6. 今日から始める「住居費最適化」アクションプラン
ステップ1:現在の住居費を完全分析(1週間で完了)
分析すべき項目
- 月々の住居関連支出の洗い出し
- 過去5年間の住居費総額計算
- 将来10年間の住居費予測
- 同等条件での購入・賃貸比較
ステップ2:ライフプランとの整合性確認(2週間で完了)
確認事項
- 転職・転勤の可能性
- 家族構成の変化予定
- 老後の生活設計
- 相続・贈与の予定
ステップ3:具体的アクション計画の策定(1ヶ月で完了)
アクション例
- 住み替えのタイミング設定
- 頭金の準備計画
- 住宅ローンの事前審査
- 物件情報の収集開始
田村さんは「もっと早く気づいていれば」と言いますが、68歳からでも十分に成果を上げています。「何歳からでも、正しい知識があれば住居費を最適化できる」これが田村さんからのメッセージです。
まとめ
田村さんの体験談から分かるように、住居費は人生で最も大きな支出項目であり、その選択が老後の生活を大きく左右します。
重要なのは、目先の支出だけでなく、ライフサイクル全体での住居費を考えることです。賃貸と購入のどちらが良いかは人それぞれですが、少なくとも「なんとなく」で選択するのではなく、しっかりとした計算と将来設計に基づいて判断する必要があります。
田村さんのように、68歳からでも住居戦略を見直すことで大きな成果を得ることは可能です。年齢に関係なく、今からでも住居費の最適化に取り組んでみてください。
あなたの人生後半がより豊かで安心なものになることを、心から願っています。田村さんのような「逆転の住宅戦略」が、あなたにとっても人生を変えるきっかけになるかもしれません。
1つのモデルハウスの見学時間は1時間以上をお勧めいたします。余裕を持って、当日の予定を組みましょう。
モデルハウス見学予約の
4つのメリット
✅ 1.サクサク見学
待ち時間なくスムーズに見学できるので、貴重な時間を有効活用できます。家族との大切な週末を有意義に過ごせます。
✅ 2.効率よく見学!
複数のモデルハウスをまとめて見学できるので、効率的に情報収集が可能です。自分に最適な住まいを一度に比較検討できます。
✅ 3.専門性の高いスタッフ
専門知識を持ったスタッフがあなたの要望に合わせて丁寧に対応。理想の住まいを見つけるためのアドバイスが受けられます。
✅4.当日のやりとりがスムーズ
事前に質問を伝えられるので、当日の見学がスムーズに進みます。重要なポイントをしっかり確認でき、安心して見学が楽しめます。